- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール
- コラム記事一覧
- プロも実践!上司から一目置かれる企画書作成術
プロも実践!上司から一目置かれる企画書作成術
2018年 09月 07日
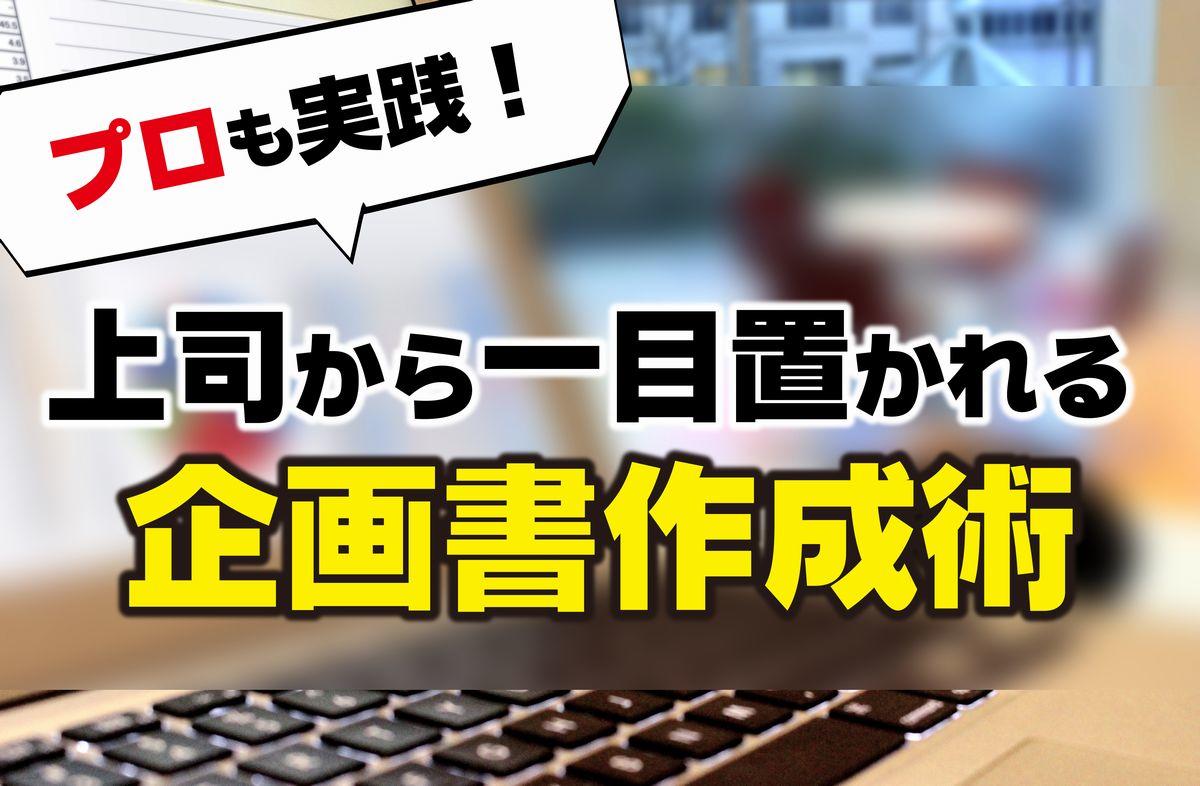
新しいプロジェクトのアイディアを企画書にまとめたけれどもダメ出しをされ、どのように作成すればよいのか悩んでいる方はいませんか。あるいはアイディアがなかなか出ずに苦労している方も多いでしょう。
実は企画書の作成では、押さえておくべきポイントがありますし、アイディアを生み出すコツもあります。そこで今回は、具体的な企画書の作成ポイントとアイディア の出し方をご紹介していきましょう 。上司に一目置かれるような企画書を作成するために、ぜひご覧いただければと思います。
目次
■企画書1つで全てが分かる
企画書はプロジェクトのスケジュールなどを細かく落とし込んだ設計図となります。そのために、1つの企画書でプロジェクトの概要などが全て把握できるようにしなければなりません。そこで、どのような内容を記載すればよいのかをご紹介します。
1.問題点の整理
最初に、企画書のテーマである課題や問題点を提示しましょう。プロジェクトを立ち上げる価値があることを納得してもらう必要があるからです。そのためには会社やクライアントが抱える問題を深掘りし、的確な解決策を導くための根本的な問題を見つけ出す必要があります。
さらにその課題が、会社にとって取り組む価値があることを示しましょう。課題や問題を解決することで、どのようなベネフィット(利益や便益などのこと) を得るのかを示すためです。
2.ゴール設定
次に課題や問題を解決した先にあるゴールを明確にします。具体的には、会社やクライアントがどのようなベネフィットを得るのかを提示します。利益確保やシェア拡大はもちろんのこと、たとえば知名度やブランドイメージの向上につながることを示すわけです。
3.解決策の提示
直面している課題とそのゴールを明示したら、次は具体的な解決策を提示します。企画書の良し悪しは、その解決策に実現性があるか否かで判断されます。そのためには主観にとらわれずに、現状分析を3C(顧客や自社、競合のこと)や4C(顧客価値や顧客コスト、利便性、コミュニケーションのこと) あるいはSWOT分析(自社の強みや弱み、機会、脅威について分析)などで行い、解決案を導き出しましょう。さらにスケジュールや予算なども添えることで、具体性が高まります。
■アイディアに行き詰まったら試したい技
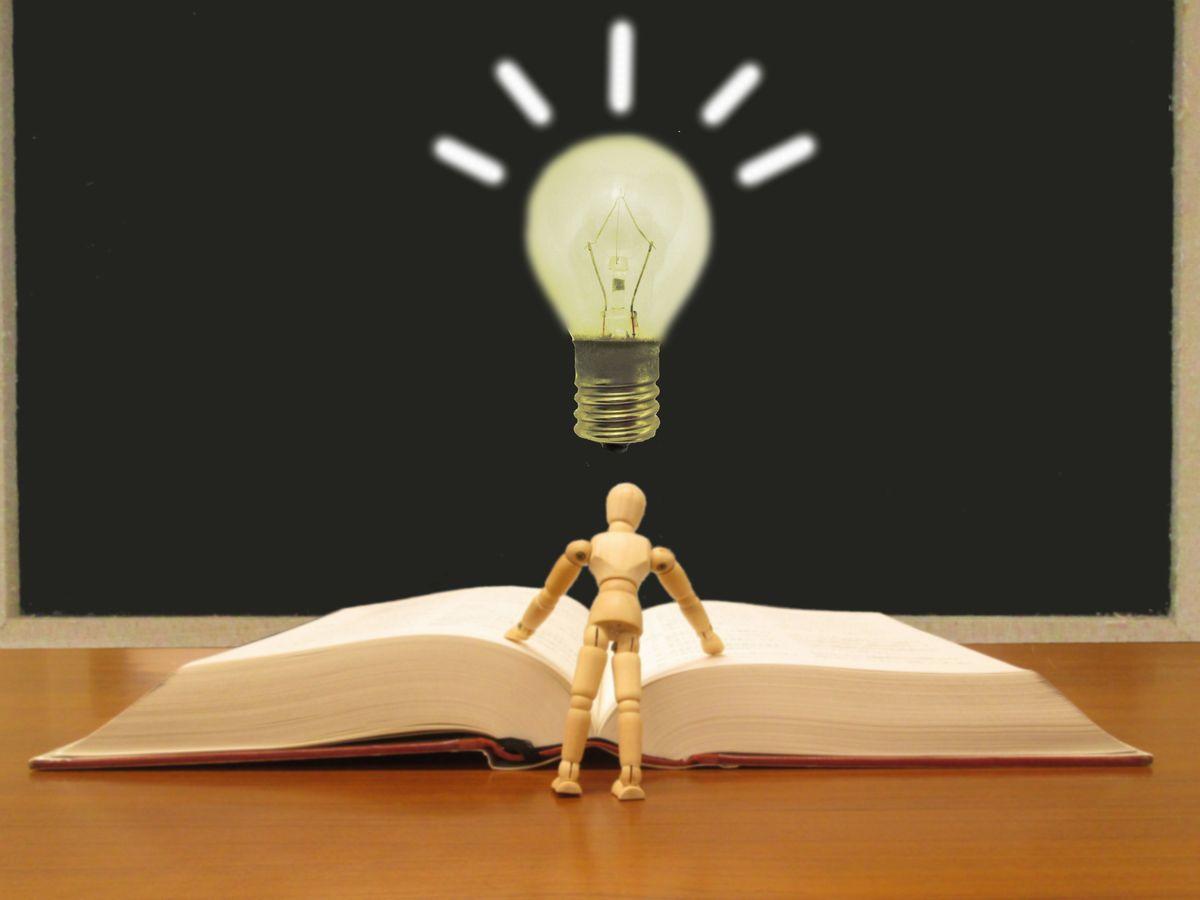
企画書の作成で必要なアイディア出しに行き詰まったら 役立つ技をご紹介しましょう。
1.頭に情報を入れて一度寝かせる
発想やひらめきは、複数のアイディアを融合させることで生まれます。そこでアイディアに行き詰まったならば、集めた情報や思いつきを全て頭に入れて一旦寝かせておくとよいでしょう。それまでに温めてきた思考やアイディアと化学反応を起こして、新しいひらめきが生まれやすくなるかも知れません 。
また時間をかけて考え続けていると、同じ考えが頭の中を回り続けて抜け出せなくなります。それよりも一度机から離れて歩いたり場所を変えたりすることで、新たなアイディアが生まれやすくなります。
2.紙に書き起こす
企画書のアイディアはパソコンではなく、紙とペンで書き出すとよいでしょう。新たなアイディアは複数の思考が絡み合い、化学反応を起こすことで生まれます。そのためには自分の頭に多くのアイディアの素を記憶させることが必須です 。
記憶は感情に結び付くと定着しやすくなります。そこで紙にキーワードひとつでも書きだすことで、その時の感情や細かな思考を筆圧や文字の形として残すことが可能です。そして書き溜めた紙を眺めていると、その時の記憶とともに細かな思考が脳の中で再生され、ひらめきを生み出すようになります。
自分の手でキーワードや思いつきを書き出す際には、付箋を使ったブレインストーミングやホワイトボードが役立ちますよ。とにかく頭に浮かぶことを感情とともに文字にすれば、脳の中で定着しぶつかり合ってひらめきにつながります。
エッサムでは壁全面がホワイトボードでできた会議室を完備しています。
■これだけは押さえておきたい!4つの企画書作成ポイント
それでは具体的に、企画書を作成するためのポイントを4つご紹介します。
1.作成:アイディア出し=1:9の比率
生み出したアイディアはすぐに企画書にまとめようとせず、じっくりと考えることをお勧めします。途中で手が止まるようであれば、それはまだ思考の時間が少ないということです。1時間で企画書をまとめるならば、9時間は考える時間に費やしましょう。
よいアイディアが生まれたら、それをどのように伝えるのかに注力しましょう。そしてロジックに穴はないか、データに不備がないかをチェックします。指摘される部分を残さないように徹底的に考えることが大事です。深みのある思考に裏付けされた企画書は説得力を持ち、聞き手を納得させることができます。
2.使う言葉はシンプルでダイレクトに
企画書の内容を絞り込むために、使う言葉もシンプルにすることが大事です。直接ダイレクトに聞き手へ 伝わるように、表現にも工夫しましょう。お弁当でいえば幕の内弁当ではなく、唐揚げ弁当を作るイメージにします。
幕の内弁当はどのおかずがメインなのか、ひと目では分かりません。けれども唐揚げ弁当は一目瞭然です。企画書も何を伝えたいのか一目瞭然にすることで、コンセプトが聞き手の頭にすんなりと入り込みます。
3.データの提示で説得力アップ

課題の創出に必要な現状分析には、説得力のあるデータが必要です。そのためには統計データや市場データなどを視覚的に見やすく提示しましょう。さらに課題を解決するだけの価値があることを、費用対効果で明示する必要もあります。
そして提示した解決策で最終的な目標を達成できるよう 明確にしましょう 。プロセス管理のように解決スケジュールの各段階において、達成可能性を数値化することでも説得力を持たせることができます。
4.原因から結論へ、論理的な流れに
企画書をまとめる際に、原因から結論へと論理的な流れにすることが大事です。現状分析から課題の提示、そしてその解決策から目標とする数値設定まで正しいロジックで進めるようにしましょう。MECE(漏れなくダブリなくすること)を意識して企画書の流れを構築 し可視化します。一本道を進むように話が流れることで、聞き手はストレスなく理解できます。
■企画書以外での注意点

企画書を作成したら、その発表でのポイントも押さえておきましょう。
1.何を話せばクライアントに伝わるのか
企画書はあくまでも書き手の価値観に基づいているので、それを理解するかどうかは、聞き手の価値観に左右されます。そこで企画書を発表する際には、聞き手との認識のすり合わせを意識しましょう。一方的にしゃべるのではなく、途中で相手の表情を見ながら理解度を確認します。提示する分析データが聞き手との世代間のずれを感じさせるものであれば、まずはそのデータの有意性を理解してもらえるように説明しましょう。
2.発言のときは身振り手振りとハキハキしゃべる
企画書は聞き手の理解を得ることが大事です。そのためには自信を持ってハキハキと話し、時に身振り手振りも加えて伝えましょう。話し手が不安げでいると、聞き手も不安になります。自信を持って伝えれば、提示するデータにも信憑性が生まれます。安心して聞いてもらうように意識して発表することが大切です。
3.クライアントの不安を取り除く
企画書のアイディア が斬新であるほどに、聞き手であるクライアントはリスクを感じ取り不安になります。そうならないために、先にそのリスクや不安の原因 に触れて、対策を明示しましょう。もちろん根拠のあるデータを提示しながら、納得してもらえる形で話を進めることが大事です。
■販促会議は貸し会議室で
このように、企画書の質によってプレゼンの説得力が大きく左右されることがわかります。企画書の質を高めるアイディアは、同じ場所で長時間こもってもなかなか生まれません。もし一晩アイディアを寝かせる時間がない時は、社外の会議室を利用してみてはいかがでしょうか。それまでの熟考からひらめきが生まれ、一目置かれる企画書にまとめることができるでしょう。
