- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール
- コラム記事一覧
- 無駄な会議にピリオドを!今すぐ取り入れられる賢い会議の作り方
無駄な会議にピリオドを!今すぐ取り入れられる賢い会議の作り方
2019年 10月 24日

明日会議か...、と気が滅入ることありませんか。ダラダラと長く、無駄の多い会議を行っている企業は実に多く、社員の不満は確実に蓄積されていきます。長くなってしまう会議の原因が、大きく分けて4つあることをあなたは知っていましたか。無駄な会議を効率のよい賢い会議に変えるテクニックを知るか知らないかで得られる利益には差が開きます。今回は、手軽に取り入れられる会議テクニックについてご紹介していきますね。
目次
■無駄が多い会議の原因はコレ!
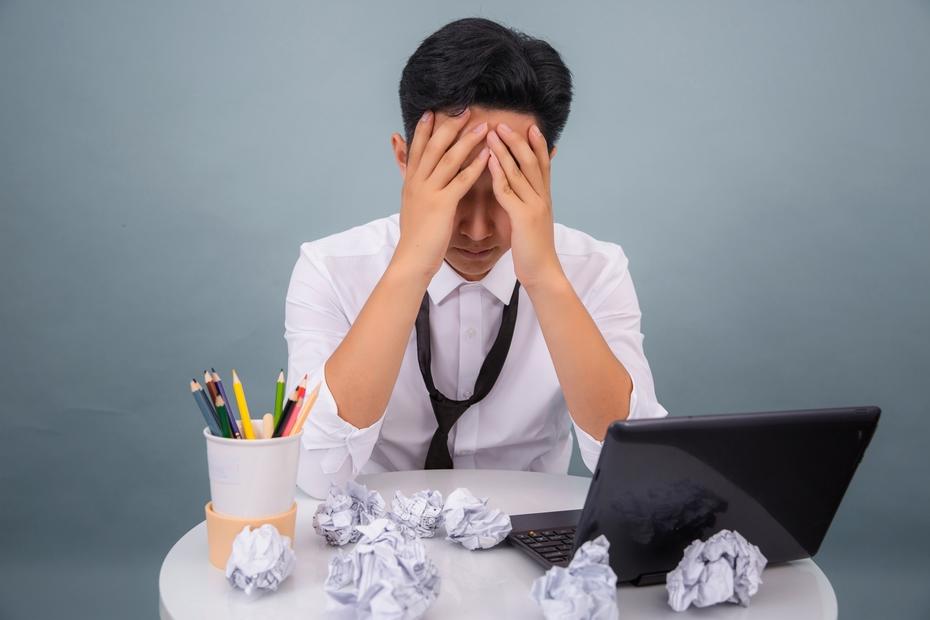
無駄が多い会議には、次の4つの原因が当てはまります。それぞれについて見ていきましょう。
原因1.目的やゴール設定がない
会議参加者に聞いてみると、みな口をそろえて「参加する必要性を感じない」、「何を決めたいか分からない」など、会議を開催する目的やゴール設定ができていないことがあります。
会議を行うからには、その場に人を集めるコストや時間に伴う生産性に配慮しなくてはいけません。せっかく会議に参加したにも関わらず、目的やゴール設定ができていないと無駄に時間と費用(人件費など)だけが失われてしまうでしょう。
また会議に使う資料として、ただ情報を詰め込んだだけの資料、あるいは解決へ導くために作られていない資料を会議で用いる企業はとても多いです。資料を作る上で、IPO(Input・Process・Output)の要素を取り入れ、一目で分かる資料作りのスキルが重要です。資料作りのためにも目的やゴール設定は必ず決めておきましょう。
原因2.肝心の議論に時間が割けない
会議を進めるにあたりIPOのどれかが偏っていては、会議で決議を取ることもできず、次回に持ち越しの可能性があります。もし持ち越しになった場合、上層部が参加する会議であればあるほど、次回開催の時間を割くことは容易ではありません。次の1と2の項目は、準備下手な人に起こりがちな原因です。
2-1.インプット要素の偏りが多い
資料説明が会議の大半を占め、会議本来の目的である意見交換や決議ができないまま会議を終えてしまう。「どんな些細な情報も取りこぼさないように」という考えから、資料作りをいきなり清書して作成しようとする人に当てはまりやすい傾向です。無駄な情報はその分、会議が長くなってしまうので、参加者に意図が伝わりづらくなってしまいます。いきなり清書するのではなく、メモなどで資料のあらすじを箇条書きするとよいでしょう。
2-2.インプット要素が不足
決議をするために必要な情報が不足し、正確な情報共有ができず不確定要素の中、話し合いを進めてしまう。たとえば、営業会議を例に見てみましょう。
ある営業所での会議の様子です。営業会議の際に提示された資料には、個々人の営業成績データのみ。このデータを元に営業利益を上げるための話し合いを行う場合、情報が乏しいために憶測での意見が展開されることがあります。「営業成績を上げるためには、個人の努力が必要なのでは?」、「いやいや、管理体制を整えた方が...」といったように、個々の自由な発言がされ収集がつきません。その結果、営業利益向上のための決議がつかぬまま会議を終えてしまいます。
本来、営業利益向上のために必要な情報(顧客ニーズや営業マンの管理体制マップなど)が会議のときに用意すべき情報だったのに、不足していたために不毛な会議で着地してしまったことが原因といえます。
原因3.雑談や脱線が相次ぐ

会議の流れが構築できないと、会議とは関係のない雑談や本題から脱線してしまうことはよく起こります。会議当日の流れとして、時間配分を行わないと時間をかけるべき項目とそうでない項目があいまいになり、ただただ時間ばかりがいたずらに過ぎ去ってしまいます。
原因4.定例会議をルーティーンで組む
企業によっては、報告会のことを会議と位置づけしているところもあるかと思います。この報告会を行っている大儀が明確であれば、特に問題はありません。しかし、ただ毎週取り組んでいるからという理由であれば、何かしら策を講じることが急務です。ルーティーンで行うことで、作業のマンネリ化や社員のモチベーションダウンにもつながってしまいます。
■今すぐ実践!!賢い会議テクニック10選

無駄な会議の原因が分かったからこそ、これらの原因を対策することで効率のよい賢い会議を見出せます。では、具体的なテクニックとしてどのような方法が考えられるでしょうか。今回は、すぐに取り入れやすい10個のテクニックをまとめました。
1.時間を区切る
無駄が多い会議ほど、ダラダラと長く会議で時間を割かれてしまいます。会議内容に合わせて時間を何分と決めることで、時間内に決断を下す後押しとなります。たとえば、情報共有の会議であれば10~15分、アイディア出しの会議であれば30~60分と決めておくとよいでしょう。
2.報告会をなくす
「本当にこの会議は必要なのか?」と根本から見直すことで、必要な会議とそうでない会議が浮き彫りとなります。また会議の仕組みをWebやチャットに変更することもひとつの手です。会議自体がなくなることで、いままで行っていた会議の時間を別の業務に当てられます。
3.会議の資料を作りこまない
会議資料を作るのに、一から全て作りこむ必要はありません。時短テクニックとして、イメージ画像や参照データを用いることで、視覚的に内容が伝わるのでオススメです。また、会議の目的に合わせて必要最低限の情報は押さえておきましょう。
4.事前に資料を配る
会議参加者へ事前に資料を配ることで、会議当日に資料説明する時間を大幅カットまたは割愛できます。会議当日は、浮いた時間を資料の補足説明や決議の時間にあてることで有意義な時間となるでしょう。
5.ファシリテーターを用意する
会議の悩みの種である雑談や脱線。この場合、会議の司会進行をする人がいないために舵取りができないことが考えられます。ファシリテーターをおくことで、話の主軸がずれたら方向修正ができます。会議において、司会進行にはコツが必要です。詳しくは、「デキる会議のファシリテーターが使っているアジェンダと便利なフレーズ9選」をご覧ください。
6.時間配分を決める
会議内容に合わせて時間配分を決めておくことで、よりスムーズな会議進行が可能です。たとえば会議の時間を30分確保したのであれば、問題定義(問題の背景や概要など)を5分、意見交換に15分、決議に10分と目安ができます。会議目的にもよりますが、より重きを置きたい項目に時間を多く配分することがポイントです。
7.午前中に行うことがベスト
仕事で疲れきって会議を行ったとしても、頭が回らず結局会議が長引いたという経験はありませんか。最近では、朝会議として午前中に会議を行い、会議で決定した項目を午後に反映、次の会議でフィードバックする取り組みが行われています。ただ、注意したいのが現代人にとって朝の会議を憂うつに思う人は多いので、開催前には社内の声に耳を傾けて判断してみるのもよいでしょう。
8.コスト意識を持たせる
会議を行っているときは、直接的な利益を生み出している訳ではないので、会議参加を疎ましく思う人も中にはいます。この解決策として、会議にかかるコスト(施設費や人件費など)を視覚化することで、会議参加者へコスト意識の植え付けを実践した外資系企業があります。その結果、会議の時短だけではなく、間接的に売上げへの貢献ができるようになりました。
9.決議を取る
会議内容に決議権を委ねることで、時短や発言への責任が伴い、参加者は真剣に議題と向き合えます。せっかく開催したにも関わらず決定権がない場合、話し合いだけで終了してしまいます。決議権がないと分かった時点で、会議を延期することもひとつの手です。
10.参加者意識を持つ
会議参加者が会議内容を他人事に捉えているようでは、会議を開く意義がありません。効率のよい会議には、参加者一人ひとりが自分の問題として捉えることが求められます。「なぜこの会議を行うと思う?」と聞かれた際に、誰もが応えられる状況が理想的です。
■効率のよい賢い会議はすぐにできる

会議を苦手に思う人が多いからこそ、会議の質を高めるテクニックは今後よりニーズが増すでしょう。会議のマンネリ化や現状維持は、企業にとって衰退という言葉が頭をよぎるのではないでしょうか。効率のよい賢い会議は、特別なツールや導入費用が必要な訳ではありません。いつもの会議にひと手間加えるだけで、会議の質に雲泥の差が出ます。
エッサム神田ホールでは、いままで数多くの企業から貸し会議室をご利用いただきました。やはり企業によって、会議には特色があると常に感じます。貸し会議室を提供する私たちだからこそ、会議の運営について専門スタッフがアドバイスすることも可能です。また、会議室の用途に合わせた「会議運営支援 」もご用意しております。まずはお気軽にご相談くださいね。
