- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール
- コラム記事一覧
- コロナ禍での集合研修はどうすべきか?
コロナ禍での集合研修はどうすべきか?
2021年 02月 26日

新型コロナウイルス感染症対策の一環で、人材育成の場である研修会は対面型からオンライン型へ移行していきました。しかし、オンライン研修では培うことの難しい課題もあり、企業によってはオンライン研修と集合研修を併用して人材育成にあたるところもあります。
今回は、コロナ禍における集合研修を行う際の注意点についてお話ししていきます。
目次
■そもそも集合研修とは?
集合研修は、研修受講生を一堂に集めて行う研修スタイルです。コロナ禍の影響でオンライン研修に代わりつつありますが、スキル系や技術系、マナー研修といった1人での受講に限界がある研修には集合研修は大きな意義があります。
■集合研修とオンライン研修のメリット・デメリット
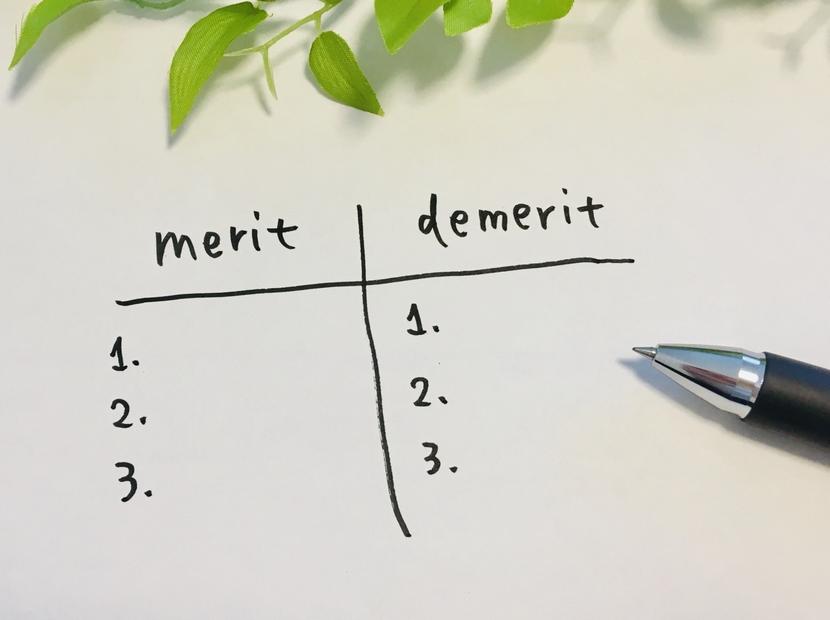
集合研修・オンライン研修にはそれぞれ次のようなメリットとデメリットがあります。
集合研修のメリット
・同じ目標をもって取り組む仲間が近くにいると体感する
同じ空間で同じ作業をすることによって、「共通運命」であるといえます。たとえば、プロ野球チームも個々人のプレーの積み重ねによって、チームの勝利を勝ち取ろうと切磋琢磨します。個人だけでの研修では決して埋めることのできない経験値といえるでしょう。
・実務に直結する内容が習得できる
知識として概要をつかめたら、実際に体を通してスキルや技術を取り入れ、実務に上手く活用する時間が必要です。個人で完結する業務であれば、自己研鑽していけば済むでしょうが、現場では他者との関りを求められることが多くあります。集合研修では、実践的な内容をバランスよく取り入れた内容を練習できます。
・講師からフィードバックがもらえる
質問した際に、講師から直接フィードバックが受けられます。研修受講生の知識レベルや理解度に合わせて伝える事が出来るため、質の高い研修が行えるでしょう。また、スキルの習得度や受講態度などを可視化させ今後の人材育成にも活用できます。
集合研修のデメリット
・コストがかかる
場所やスケジュール調節、講師の手配など、時間とお金がかかります。コロナ禍前に利用していた会場もソーシャルディスタンスの観点から場所の見直しをしなくてはいけなくなり、研修手配の担当者としても手間がかかることでしょう。一定の広さを確保できる貸しホール・貸し会議室を上手く活用してみるのもひとつの手です。エッサム神田ホール2号館にある大会議室は、高さ・広さともに兼ね備えているため、集合研修でも広く間隔を保って行えます。詳しい席レイアウトは、こちらをご覧ください。
・研修受講生の知識や技術レベルにバラつきがある
集合研修は足並みをそろえて進めるため、個々人の知識レベルや理解度が異なるとスケジュール通りにいかないことが考えられます。そうならないためにも、研修内容を事前に周知させたり、必要な知識の事前学習を取り入れたりすることが必要です。
オンライン研修のメリット
・コストを抑えられる
PCなどのデバイスがあれば受講ができるため、場所にとらわれることなく受講できます。そのため、研修参加のための交通費や宿泊費、会場費などのコスト削減が見込めます。全国展開している企業であれば、幅広い対象者に向けて実施可能です。
・個人のレベルに合わせて受講可能
受講内容を個々人のレベルごとに合わせて受講でき、理解できるまで繰り返し受講できます。自分のペースで学習が進められるのも魅力のひとつです。
オンライン研修のデメリット
・実践が求められる研修には不向き
知識レベルである程度理解したといっても、現場で知識を活かせるかどうかは別問題です。受講内容に合わせたペアレッスン・グループレッスンを上手く併用するべきでしょう。
・モチベーションの維持
個人で時間を見つけて学習することはできても、質問ができなかったり、フィードバックが得られなかったりするため、モチベーションの維持が難しく挫折してしまう人もいます。
■コロナ禍での集合研修を行う際の注意点

コロナ禍における集合研修では、感染を防ぎつつ適切な研修会運営が大前提となります。参加するにあたって十分な感染予防、感染を広めないための準備が必要です。感染予防に取り組んだ上で、より良い集合研修にしましょう。
(1)研修受講生の安全確保
・開講前の体温測定
当日、自宅にて検温を行い平熱より高く、発熱があれば自宅待機する。また発熱がなくても、息苦しさや強いだるさ、味覚・嗅覚障害、軽度の咳や喉の痛みなどの症状があれば、無理せず休みましょう。
その他、同居人・家族に感染者がいた場合や感染者との濃厚接触者で自宅待機の指示を受けている場合も研修へは欠席するようにしましょう。
・マスク着用を徹底させる
受講者には必ず、マスク着用を徹底させましょう。マスク着用で飛沫感染のリスクは大幅に改善されます。マスク着用が難しい場合には、口にハンカチやティッシュを当てるなどして、飛沫を防ぎましょう。
・咳エチケットやこまめな消毒などを自発的に行う
研修受講生として、1人ひとりが節度を守って感染をしない・させない・広げない行動が大切です。
(2)主催者(運営スタッフ)の安全確保
・講義中のマイク・マスクの徹底
マイクの使いまわしによる感染リスクを避けるため、発言者を制限する。講師に1本のマイクを渡し、グループ・ペアで代表者に1本渡しておくといいでしょう。マイクの使用後には、アルコール消毒を実施します。
また、発言しないときにはマスクの着用を徹底しましょう。
・参加者の体調管理
研修受講生・研修運営者の当日の体調を把握し、場合によっては欠席する。
・席の配置を広くとって、ソーシャルディスタンスを確保する
人と人との距離が隣接しないように、できるだけ2m(最低1m)の距離を保てるようにしましょう。
・咳エチケットやこまめな消毒、声の大きさなどを周知させる
感染予防をおろそかにしていては、せっかくの取り組みが無駄になってしまうこともあります。研修開催前に、参加者への周知・協力の呼びかけを忘れてはいけません。
・研修中に体調不良になったら帰宅させる
研修中に体調を崩してしまったら、直ちに帰宅させ場合によっては病院への受診を指示しましょう。感染の可能性もあるため、その後の体調の経過について必ず確認を行います。
(3)研修会場の対策
・研修参加者、全員の検温
会場への入室にあたり検温するよう徹底しましょう。最近では、非接触型の体温測定でスムーズに検温ができるので、取り入れてみるといいでしょう。
・ドアや窓の開放・換気
研修中にもこまめな窓の開放で室内の換気を行う。
・ドアノブや机などのこまめな消毒
物を介して広まる間接接触感染を防ぐ。
・グループワークやペアワークのメンバーを記録
万が一、感染が確認された場合、迅速に連絡を取れるようにするためにもメンバーの記録や連絡先を把握しておきましょう。
■感染対策を徹底して集合研修を成功させよう!

新型コロナウイルスの最新情報が入り次第、新たな対策項目が増えることも十分に考えられます。感染を防ぐためには、1人ひとりの行動が重要です。感染しない・させない・広げないために、普段からこまめな消毒やマスクの着用をしていきましょう。
会場選びの際には、参加人数よりもゆとりある席数、席配置が可能か会場に問い合わせを行いましょう。
エッサム神田ホールでは、新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを独自に設け、ご利用者様が安心して使えるよう感染症予防に努めております。また、研修内容に合わせて会場を手配でき、ゆとりある席レイアウトも可能です。ご不明点等ございましたらお気軽にご相談ください。
