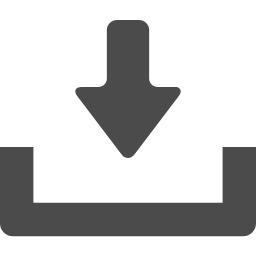- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール
- コラム記事一覧
- デキる会議のファシリテーターが使っているアジェンダと便利なフレーズ9選
デキる会議のファシリテーターが使っているアジェンダと便利なフレーズ9選
2022年 06月 30日

大多数の人は会議を苦手としています。
どのような会議の場であっても、会議に喜んで参加する人というのは、ほとんどいないものです。
ましてや、会議の進行係を仰せつかってしまったら、もう心臓の鼓動がマックスを通り越して、食事も喉を通らなくなるかもしれませんね。生きた心地がしないかもしれません。
最近では、会議の生産性を上げるために、「ファシリテーター」という中立的な立場から議事進行を行うスキルが求められています。会議の進行や場の雰囲気を円滑にすることで、無駄な会議を省くことに一役買っています。ですが、いきなりファシリテーターを任されても、誰もが容易に対応できる訳ではありません。
では、そんな難役を任されたならどのように進行していけばいいのでしょうか?ファシリテーターがどのような物なのか、会議進行に今すぐに使える便利なフレーズとコツをご紹介いたしましょう。
ファシリテーターのコツを知りたい人は「実践編!9つの便利なフレーズ」からご覧ください。
■そもそもファシリテーターとは?

ファシリテーターとは、物事を円滑に進行するための中立的な立場から舵取りする人のことを言います。参加者の意見を引き出したり、目的達成のために状況に応じて会議をサポートしたりする重要な役割です。
ファシリテーターと司会者の違い
会議における司会者とは、用意したタイムテーブルに沿って運営・進行する人のことを指します。その一方、ファシリテーターは、進行だけでなく参加者のアイディアを引き出す手助けをしたり、話が脱線したら本題に軌道修正したりします。
最近、テレビ番組での司会者をMC(マスター・オブ・セレモニー)と呼ぶことが増えたのも、個々の能力を引き出して番組全体を盛り上げる人としてのニーズが高まったことが伺えますね。
会議の規模や内容によっては、司会者とファシリテーターを別々で選任することもありますので、それぞれの違いを押さえておきましょう。
ファシリテーターを会議に選任するメリット
誰しもダラダラと生産性のない会議に参加するのは嫌なことでしょう。ファシリテーターを会議で選任することで、次のようなメリットがあります。
- 会議のゴールが明確になる
- 新しいアイディアを生み出すサポーター
- 時間にコミットして会議運営できる
- 会議参加者みんなの合意が必要なときのまとめ役
- オンライン会議での舵取り
このように、ファシリテーターを選任することはさまざまなビジネスシーンで有効と言えます。もしまだファシリテーターがいない会議をしているのであれば、試してみる価値アリです!
ファシリテーターの役割
ファシリテーターの役割は多岐に渡ります。また、オンライン会議の需要が高まり、新たな役割も加わりましたので、ひとつずつ見ていきましょう。
雰囲気作りの担い手
会議を進行する上で、参加者の意見を引き出すために議題の共有や発言時のルール設定など、雰囲気作りは大切です。会議の話がヒートアップしてしまったときには、一度話を区切ってリフレッシュすると良いでしょう。
参加者の意見を引き出す
どんな意見でも、尊重すること。ファシリテーターは、誰よりも「聞き上手」になることを心がけましょう。もし発言が上手くできない人がいたらフォローすると良いですが、その際には中立の立場を維持しましょう。
出た意見を整理する
時間内で挙がった意見を元に、情報を整理していきます。このとき、ホワイトボードなどに付箋で出たアイディアを貼り、意見の視覚化をすることで、参加者が分かりやすく状況の把握ができ、意思決定の支援にもなります。
結論をまとめ、参加者の合意を得る
話し合いの要点をおさらいし、参加者から合意を得た内容を確認していきます。会議の結論をまとめ、参加者全員の理解・合意を得ます。その結論を元に、参加者ごとに今後どのような取り組みをしていくかを明確にしていきましょう。
オンライン会議でのルール設定
オンライン会議では、参加者ごとにインターネット環境が異なるので、事前に参加できるのか確認が必要です。また、対面での会議と違い、オンラインでは、複数人が同時に話すとスムーズな運営が難しいため、発言時のルール設定を設けましょう。オンライン会議と同時にホワイトボードなどのWebツールを活用することをオススメします。
■ファシリテーターに求められるスキルとは?

ファシリテーターとは、ファシリテーション(会議の舵取り)を行う人のことを指します。ファシリテーターに求められるスキルは、4つあります。
1.会議の目的と種類に合わせて準備
会議には、大きく分けて「コミュニケーション会議」、「議論会議」、「意思決定会議」の3種類があります。会議の目的に合わせて、事前準備に差がつきます。
コミュニケーション会議
参加者に情報を共有することが目的になります。報告や連絡事項、知識共有の場として活用している企業も。参加者は、発言する内容を事前に考え、意見を固めて臨む姿勢が求められます。
議論会議
企画発案や事業部ごとの問題発見など、提案が目的になります。会社の方針や運営に関わることが多いため、管理職が参加することが多いです。企業によっては、ブレインストーミング(アイディアの連鎖反応)で立場の垣根を越えて発言できるようにするため、社内目安箱を設置しているとこもあります。(1) 議論会議には、賛同意見だけではなく、否定意見の要点や疑問点などさまざまな発言が挙がります。参加者は、会議の議題に合わせて資料準備や論点をまとめておくと、当日の会議を慌てることなく向かえられるでしょう。
意思決定会議
コミュニケーション会議と混同しやすいですが、意思決定会議は会議において決定した事項を元に、プラン立てや現場フローへの落とし込みを最適化させることが目的になります。参加者は、自身で任されている仕事に対して、決定事項の影響を考慮して不安や疑問点の書き起しを行いましょう。この時、伝達者の理解度が重要になりますので、考えられる質問に対して準備しておくと良いでしょう。
2.会議において中立の立場

いままで議題に対して、賛否両論になり収拾がつかなかった経験が誰にでもあるのではないでしょうか。
会議をスムーズに行うには、双方の意見を聴き、意見の円滑化が必要となります。また、発言内容によっては、具体的に煮詰めるべきか、あるいは抽象的に話をまとめるべきかの配慮が大切です。参加者によっては、言葉の意味が異なることがあります。例えば、「これで大丈夫」という発言があった際、受取り手によっては、容認されたと解釈する人も居れば、疑問点がまだあると捉える人も居ます。このように、人によって言葉への定義が違うので、注意が必要です。
3.会議進行時の舵取り
司会進行をする際に、発言させることに重きを置く人をよく見かけますが、ファシリテーターには参加者に考えさせるスキルが求められます。参加者に平等に考えを聞くことは大切ですが、意見交換会で終わる会議は非生産的です。まずは、会議の目的をはっきりさせ議題に対して考える時間を設けてみましょう。この時、付箋やペンを用意しておくと紙に書き起こすことで意見の視覚化ができます。 次に紹介する9つのフレーズで会議スタートからゴールまでを細かく見てみましょう。
4.タイムマネジメント
限られた時間を円滑に進行できるかは、ファシリテーターの腕の見せ所。おおよそのタイムテーブルを設定することで、スムーズな運営が可能です。しかし、状況によってはより良いアイディアを引き出すために予定時間の見直しをその場で行うなどの経験を積むことが鍵です。
■実践編!9つの便利なフレーズ

会議の始まりから終わりまで、各場面のお決まりフレーズを見てみましょう。
(1)会議の開始宣言!お決まりのフレーズ
会議の始まりを告げるフレーズです。毅然とした態度で使いましょう。
「では、時間が参りましたので本日の会議を始めさせていただきます。本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。」
このフレーズの後に、自分自身の所属部署や名前を名乗っておくのも定番のフレーズの一つでしょう。
1-1.参加してくれた感謝をこめて挨拶を
さて、会議に参加する面々は、その会社の重要な幹部や重要な役割を担っている中堅社員さんたちです。
まずは集まってくれた方々への感謝と敬意を込めて、丁寧に参加者たちの慰労の念を示しましょう。
1-2.つかみは簡潔にはっきりと
最初の「つかみ」ともいうべき序盤の切り出し方を曖昧にしてしまうと、参加者たちからマイナスのイメージ――「この人物で大丈夫なのか?」という疑念を持たれてしまう可能性もあります。
ここは余計なアドリブを入れて切り出すよりも、定番中の定番的な切り出し方で、会議のスタートを宣告しましょう。
(2)本題に入る前に、時間を意識させておく

会議は限られた時間でその会議の目的を果たす必要があります。
もし、決められた時間で結論に至らなかったら、その会議は「無駄」となってしまいます。
したがって、時間内に結論をださせるための工夫が必要です。
そのために重要なフレーズはこちらです。
「本日のテーマは「○○」で、「××時までに」で「△△」を決定させます」
決められた時間内に目的を達成しやすい状況を作りやすくなります。
2-1.会議のゴールを宣言する

会議の本題に入る前に、ガイダンスとして、「議題」、「時間」、そして「会議のゴール」を宣言してください。
会議のゴールと終了時間を明確にすることによって、時間の意識と決めるべきことが明確化された状態で会議がスタートできます。
また、これを宣言することにより、会議の参加者が「時間内に終わらせなければならない」という意識のもと、会議に参加してもらえます。
会議を冗長化させず、かつ実りのあるものにするためにもこの「宣言」は非常に重要となります。
2-2.アジェンダを元に会議のテーマを細分化して、細かいタイムマネジメントを行う
会議の流れを要約した「アジェンダ」というものを用意しておけば、参加者全員が会議の流れを認識してくれるので非常に有効です。
実際にデキる会議のファシリテーターは必ずアジェンダを準備します。
アジェンダにおいて必要な項目は、日時、場所、参加者、タイムスケジュール、配布資料になります。この5つは、参加者に周知しておくことによって、事前に個々の意見を考えられるので、有意義な会議の土台作りといえます。 アジェンダのテンプレートを用意しておくと、時短にもなります。
そのうえで、決定までのプロセスを細分化できるのならば細分化し、最終的に決定させたい事項を決めるまでのチェックポイントとそのチェックポイントを決めるための時間を区切ってください。
事前に紙ベースでアジェンダを作成するか、もしくはホワイトボードに記載の上、それぞれの小議題に対し「このテーマは10分で決めます」と細かく時間を設定します。
結論を決めるまでに何がポイントになるのかを明確化し、時間を決めることで、より緊張感のある会議になり、時間内に結論を導き出せるでしょう。
(3)長々だらだらと話す人がいるとき

会議を行う際に必ずいらっしゃるのが、時間を無視してだらだらと話を続け、会議を冗長にしてしまう人。自分を大きく見せて権威性をひけらかしたいのかもしれませんが、正直「空気を読めない」参加者です。
本人は満足かもしれませんが、冗長な話は、会議をあらぬ方向に脱線させ、進行の妨げにもなります。それまでいい流れできた会議が突如止まってしまっては、参加者の人件費の無駄ともなり得るのです。
そのような状況を避け、円滑に会議をとりおこなうために、切り札となるのはこちらのフレーズです。
「つまり○○さんのご意見は、~~ということでよろしいでしょうか。」
「すいません、この件に関して○○さんの意見を伺いたく思います。」
会議を取り仕切る際には、長々と喋る人をどのように対処するかが求められるのです。
3-1.話の要点を確認する
一人の人に長々と話されても、他の参加者が要点を理解できないというが往々にしてあります。そんなときは、「つまり○○さんのご意見は、~~ということでよろしいでしょうか。」というふうに、長々と話す人の話の要点を抽出することです。
冗長的に話す人から「その理解で問題ない」との合意が取れれば、参加者全員が何を言いたいのかを理解し、改めて潤滑な会議が再開されることでしょう。
3-2.時には話を強制的に切る

長くだらだら話をする人は重ねて冗長に話す傾向にあります。
それは、要点をまとめて話す能力がないからか、上述のようにただ権威性をひけらかしたいかのどちらかです。
ずっとそんな調子では、会議の時間、参加者全員の時間を無駄にしてしまう可能性も否定できません。
その際は、「すいません、この件に関して○○さんの意見を伺いたく思います」といったように、あえて強制的に話を切って、他の参加者に話を振っていくことも重要です。
少しドラスティックなやり方かもしれませんが、同じような状況をその会議の中で作らないようにできるという点では非常に有効な策です。
余談ですが、会議は最低限の人員で行うことこそが、迅速な決定のポイントとなります。
このような無駄な時間を発生させる参加者は可能な限りメンバーから外しておくことも重要です。
このテーマとは若干異なりますが、参加者においても「無駄は切る」というのも重要なことを認識してください。(決裁権のある上位層の人が冗長な話しをする人であれば少し厄介ですが...)
会議の進捗にしてもそうですが、最少の時間と力で、最大限の効果を発揮させることが求められます。
同時に、無駄な会議は時間生産性をあげる上で、ときに悪とみなされます。
そうならないようにするための工夫は常に行ってください。
(4)脱線したとき

議論に熱がこもってくると、どうしても本題から脱線してしまうことも多々ありますね。そういった際の便利なフレーズを考えてみましょう。
「○○さんの意見は非常に的を射た素晴らしい意見だと思います。ただ、本会議の趣旨からはちょっと離れてしまったようですので、その話は別の機会に伺うとして本題に戻りたいと思います。」
4-1.脱線した議論を軌道修正するのはファシリテーターの役目!
初めてファシリテーターを任された身となった時、最も苦労するのは場の雰囲気を元の状態に戻す作業ではないでしょうか?
会議の場に皆が慣れてくると、当然ながら議論の中身も熱を持ってきます。
そう、会議の場は自分自身をアピールできる重要な場でもあるからです。
参加者は、なんとか自分の意見を重役さんたちに認めてもらおうと必死になってきます。
しかし、皆が皆、自分の言いたいことばかり言い合っていては、とても会社の会議という論理的な場にそぐわなくなってしまいます。
そんなムードをファシリテーターは冷静に見て取って判断し、会議が横道に逸れすぎないように軌道修正しなければなりません。
4-2.軌道修正のさじ加減は、場数を踏んで学ぼう!
会議が脱線ムードになったならば、ファシリテーターは半ば強引にでも、議題を元の本題に戻していく義務があります。
ところが、ヒートアップしている人の意見を強引に却下してしまうと、その人から個人的な恨みを買ってしまい、後々、自分自身に火の粉が飛んでこないとも限りません。
よってこの話を元に戻すという作業は、ある程度の場数が必要な作業といえるでしょう。上記のフレーズを使う際も、タイミングと切り出すときの声のトーンが必要になります。発言者の意見を肯定したうえで議題を本題に戻す。これをこなせるようになったら、あなたはプロのファシリテーターとしてやっていけるかもしれませんね。
(5)たくさんの意見が出て、一度落ち着きたいとき

議論が盛り上がってきたとき、もしくはさまざまな意見が出てきた際には、ときに会議にまとまりがでず、混とんとし、時間内に結論が出なくなる恐れがあります。
また、時間内に会議が終わらないだけではなく、会議の中で導き出すべき「結論」にまで話が及ばなかった場合は、ただ時間が無駄に過ぎただけということになります。
その時には会議が混とんとしないように、一旦ここまでの会議の内容につい整理をしてみてください。
有効なフレーズはこちらです。
「いったんこのあたりで、出てきた意見を整理しましょう」
5-1.話を整理して会議を立て直そう
出てきた意見を板書するなどして整理し、議論中のテーマにおけるポイントをまとめ、今後の会議の方向性について指示してください。
話のポイントをまとめ、改めていま話すべき議題を明確化し、またそれを共有することで、混沌とした会議が落ち着きます。話を適正に整理することで、ここからの会議が最短距離で進行するようになります。
会議は、まったく滞らず、すべてが順調に進むことはまずありません。
話がまとまらなくなったときは、常に話を整理し、適正な状況にもっていこうと常に意識をおいてもらえたら良いでしょう。
(6)次の議題へ移るとき

会議進行は時間との闘いです。
仮に貸し会議室などの会場を2時間の予定で借りているのであれば、ファシリテーターは頭の中で時間の進行と会議の進み具合の両方を天秤にかけながら司会役を務めなければなりません。
「○○の件はこれを持ちまして終了いたします。では、次の議題に移らせていただきますが、皆さん、異議はございませんでしょうか?」
6-1.司会者は残り時間も意識しよう
司会者とは別に、タイムキーパーの係を誰かにお願いするのもよいでしょう。
ほとんどの場合、会議の進行表が資料として参加者に配られていたり、ホワイトボードに書かれていたりするものなので、参加者の方も議題の移行を納得してくれることでしょう。
6-2.議題の移行は空気を読んで冷静沈着に
ファシリテーターは常に相手を尊重し、間違った意見や議事進行の妨げとなるような行動に対しても常に冷静沈着に場を収めていく能力が求められます。
まだ議論が十分に話し終わっていない状態なのに強引に次の議題へ移ってしまったりすると、真剣さのない形だけの会議という印象を植え付けてしまうこともあります。
ファシリテーターが強権を発動して一切を決めていくような振る舞いは、健全な会議の進行を大きく妨害してしまうということです。
ファシリテーターは参加者の顔色も伺いながら、次の議題へ移ってもいいタイミングなのか、否かを嗅ぎ分けて、上記のフレーズを使うべきかどうかを判断しましょう。
(7)意見が出ないとき

毎回、活発な意見が飛び出してくれたらいいのですが、そうは簡単には進まないのが会議というものです。お通夜ムードに陥らないようなフレーズを紹介いたします。
「どうでしょうか?他に意見のある方はいらっしゃいませんか?」
定番のフレーズですね。
7-1.行き詰まりを乗り切るのもファシリテーターの仕事
ハッキリ言って、このフレーズを使ったからと言ってすぐに活発に意見が出るとは考えにくいかもしれません。
しかし、この局面を乗り切るのもファシリテーターの大事な役目です。
進行が滞るようならば参加者を指名して当てていく、というのも古典的な方法。しかしこれを多用してしまうと、ファシリテーターは自信が無いように見えてしまうこともあります。
7-2.一度上の人に話を振ってみる
なかなか意見が出揃わず、進行が思うようにいかないときは、役員クラスの人に一旦話を持っていくというのも一つの手段でしょう。
案外、現場と役員クラスの距離が確認できる場面になるかもしれませんよ。
(8)意外な質問があがって戸惑ってしまったとき

ときには会議の中で、自分自身もほかの参加者も想定しなかったような意外な質問が飛び出すことも充分にあり得ます。
「その質問は本当に必要なの?」と、困ってしまった経験や、自分のアイディアの盲点を突かれてハッとさせられた経験もあることでしょう。そんなとき、あまりに不意を突かれて硬直するような事態だけは避けたいものです。
このような「意外」な質問がでたときに使えるフレーズはこちらです。
「なぜ、疑問に思いましたか?」
質問者が疑問に思った理由を確認してください。
8-1.重要なのは、その疑問の本質を知ること
一見いらない質問に思えたときでも、その背景が分かればその「いらない」質問は重要な切り札となります。
相手の質問が出た理由・背景を知ることで、「そんな視点があったのか」という深い理解につながり、議題をクリアするためのよい起爆剤になり得るのです。
戸惑わず、質問の意図を理解するよう努めてください。
上のフレーズを使って疑問に思った理由を尋ねても、なお質問の意図が分からない場合は、質問の内容を細分化し、分けて考えてください。
また、あなたがわからなかったとしても、会議の参加者が明確にしてくれることもあるでしょう。「答えられる方いらっしゃいますか」と参加者に話を振ってみるのもオススメです。
参加者全員の納得が得られ、深い理解に変われば素晴らしいことです。
(9)終盤

さて会議も無事に進行していき、いよいよ最終段階へと進むことができました。「終わりよければすべてよし」ということわざ通り、最後の締めをしっかりと決めておきましょう。
「それでは丁度いい時間となりましたので本日の○○会議、これにて終了させていただきます。本日はお疲れ様でした。」
こんな感じで無事に締めることができる会議ならば、その会議は概ね、弊害もなく終了できたことでしょう。
ファシリテーターを仰せつかったあなたとしても、大きく安堵することに違いありません。
9-1.物事がうまくいかないときも客観性を失わずに
会議というものは、毎回平穏無事に終わるとは限りません。
業績が芳しくなかった人の報告などを聞くと、あなたもその仕事の厳しさをわかっているだけに、進行に「情」が入ってしまいやすくなってしまうでしょう。
しかし、それが許されないのがファシリテーターの役割です。常に客観的に、そして冷静に、一つ一つの案件や議題を処理していく姿勢でいましょう。
■まとめ~会議は避けられない!ならば楽しもう!
いかがでしたか?今回は会議のファシリテーターを初めて担当する方や、まだまだ議事進行役に不慣れな方の役に立つようなフレーズをご紹介しました。
冒頭でも触れましたように、会社の会議というものを心から好きだという人はほとんどいないかもしれません。
しかし、会社という組織に所属するからには、どんな業界であっても会議というものは存在します。避けて通るわけにはいかないでしょう。
そう思えば、会議は自分自身を売り込む場だと割り切って、乗り切るよう心がけるほうが、長い社会人人生、よっぽど有意義になるのではないでしょうか?
そして、会議の場所を洗練された貸し会議室に変えてみると、会議へのモチベーションも上がります。
たとえば1000円カットの床屋さんよりも、店内がオシャレな美容室に行くほうが、その日の美意識も高くなりますよね。それと同じ理屈です。
もしあなたが、会議をセッティングする立場にあるのであれば、ぜひ一度貸し会議室の下見にいらしてみてください。庭園が併設されていたり、音響設備が豪華だったり、その利便性や洗練度にきっと驚かれることでしょう。エッサム神田ホールでは、NURO回線を取りいれているため、オンライン会議やウェブセミナーの開催設備も充実しております。
エッサム神田ホールの予約や下見について詳しくは、下記を参考にしてください。
参照元:
(1)^ 目安箱 | 株式会社サイバーエージェント,
https://www.cyberagent.co.jp/corporate/message/list/detail/id=20112
2016年10月27日の記事を再編集しました。