- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール
- コラム記事一覧
- 新入社員研修に求められる内容とは?カリキュラム作成における6つのポイントを伝授
新入社員研修に求められる内容とは?カリキュラム作成における6つのポイントを伝授
2024年 04月 30日
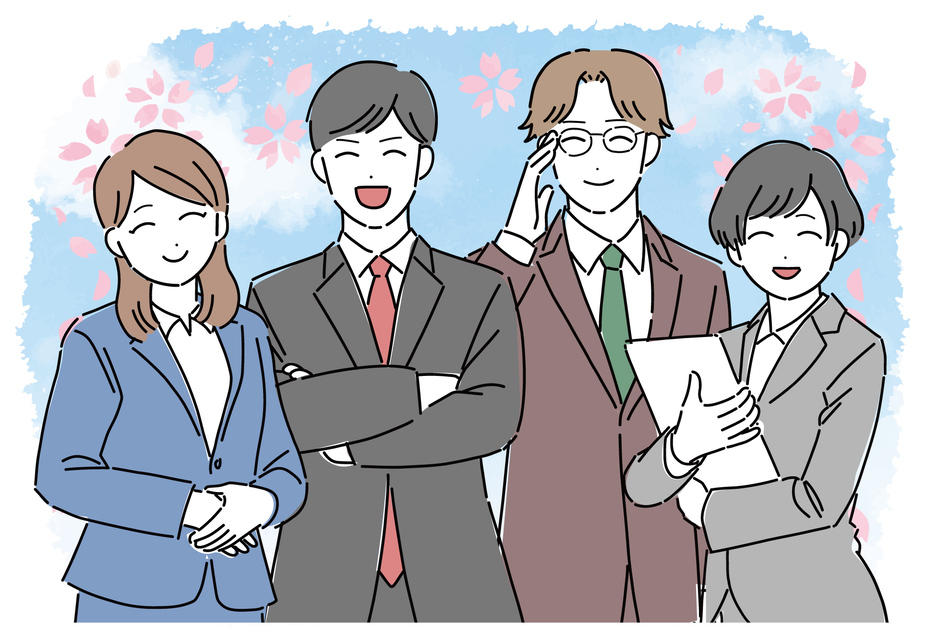
アフターコロナによって、当たり前になりつつあるオンライン化。普段の業務だけではなく、採用や研修など幅広い場面で取り入れられるようになりました。コロナを経験し、いままでの新入社員研修では太刀打ちできないと壁にぶつかった人事担当者もいるのではないでしょうか。
今回は、アフターコロナでの新入社員研修の変化や研修カリキュラムの作成方法についてお伝えします。
目次
■新入社員研修とは?
| 意味 | 新入社員向けの研修。 |
|---|---|
| 類語 | 新人研修、新卒研修、内定者研修、入社前研修 |
日本の企業で多く、取り入れられる「新入社員研修」。中途採用のような即戦力とは異なり、中期・長期的に渡る企業の中核を担う人材として新卒採用を取れ入れている企業は多いです。新卒採用した人材の育成の場として新入社員研修が実施されます。名称については、企業における研修の開催時期や対象者によってさまざまな名称が存在しますが、どの研修も目的や研修内容は似ているので、ご安心ください。
■新入社員研修はいつ、どのようなことを行うの?

研修期間は企業によって前後しますが、多くの場合、1週間ほどの期間を設けています[1]。企業規模が大きい企業では、3週間以上の期間を設けている企業もありました。
研修内容は、次の3つを中心に構成されます。
(1)社会人としての基本的なビジネスマナー
なぜ社会人にビジネスマナーが求められるのか。それは、「信頼できる人」を示すための手段として活用されるからです。これから1人の社会人として仕事に従事するにあたり、さまざまな人・会社との出会いがあるでしょう。新人とはいえ会社の名前を背負って仕事するため、相手からの信頼を得るためにもマナーは必要です。また社内でも仲間と協力して仕事するため、同僚や上司との信頼関係を構築することにも役立ちます。
(2)心構えを身につけるための導入研修
学生から新社会人として新たな門出を迎えることで、心機一転で新しい環境に溶け込もうとする人もいるが、なかには自主的でない人も。そこで社会人としての心構えや自社理念、コミュニケーション研修を導入する企業も存在します。入社後すぐに実践ではなく、会社の考えを通して一社会人として主体性をもった言動や行動を学ぶ場を設けることで、企業理解を深めて仕事に従事することにもつながります。
(3)ロジカルシンキング研修
ロジカルシンキングとは、物事を論理的に考えるあるいは説明する方法のこと。ビジネスの現場において、問題を見つけ出し、事実確認・検討材料を元に筋道を立て、第三者に矛盾なく説明できるスキルは、新入社員や中堅社員、経営者に関わらず求められる能力です。ロジカルシンキング研修によって、物事を俯瞰してとらえ、問題点の理解や解決策の立案などを鍛えられます。
■なぜ新入社員研修を実施するのか?
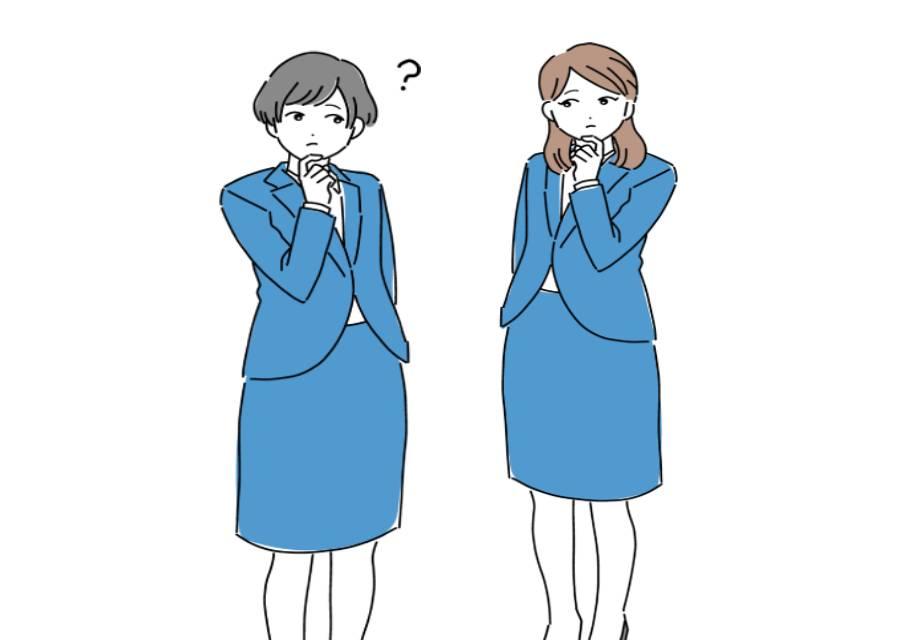
研修の目的として、次の3つが挙げられます。
(1)仕事に従事するための土台作り
先ほど挙げた研修内容は、これから仕事をするための土台作りといえます。学生のころはスクール形式で受動的に学んでいましたが、今後は多くの人との関わりを通して学ぶ必要があります。そのためにも、相手とのコミュニケーションや自分の考え方を伝える方法はなくてはならないスキルです。実際の仕事は、現場で先輩社員によるOJTによってスキルを獲得します。
(2)先輩社員との交流の場
研修期間中は、会社によっては外部から人を呼んで講義することもあるが、多くの場合、社内にいるメンバーが直接教えることがメインになります。
研修内容によっては、数年先に入社した先輩社員が教える時もあれば、部長、社長などが教えることも。研修を通して、新入社員が社内の雰囲気やメンバーと接することで、緊張が徐々にほぐれていくでしょう。
また、入社して期待に胸を膨らませる人もいれば、ここでやっていけるのかと不安を募らせる人もいます。新入社員の持つ悩みは、先輩社員も同じように抱えていた悩みでもあります。先輩社員とのコミュニケーションによって、不安の解消や悩みの解決の場として活用している企業は多いです。
(3)同期との関係構築
同じ会社に入社するため、価値観や考えに共感を抱きやすいという特徴があります。同じ課題に取り組む仲間として結束を深める場としても重要です。会社は、フォーマルな場で簡素な人間関係になりやすい特徴があります。その点同期とは事業部が異なっていても、会社とは別軸で関係性を構築しやすい特徴があります。そのメリットとして、同期の頑張りに励まされたり、奮い立ったりなど、切磋琢磨による相乗効果が期待されます(この効果を「ピア効果」といいます)。同期との結束が深いと、早期離職の予防にも貢献します。
■コロナによってもたらされた新入社員研修の変化
コロナの影響で新入社員研修には大きな変化が生じてきました。三密を回避する施策として、オンライン面接やオンライン研修が導入され、安心・安全な環境化で人事に取り組めました。
コロナ前は当たり前だった会場設営や研修制度は、オンライン化によって滞りなく実施できている企業も多く存在します。その一方で、新たな問題が浮き彫りになりました。
オンライン化によって、対面では当たり前に行ってきた非言語コミュニケーション(ジェスチャーや雰囲気など)が希薄になり、会社への愛着や親密性の構築が難しくなりました。たとえば、同期との関係でいえば、オンライン上で交流があっても知り合い程度の認識であって、仲間意識は少ないという人も中にはいます。人とのつながりがないことで、帰属意識やメンタルヘルスの悪化などが考えられます。
オンライン化による恩恵と問題点を知った上で、研修内容に合わせた対応力が、今後企業に求められているのかもしれません。
■新入社員研修のカリキュラム作成方法
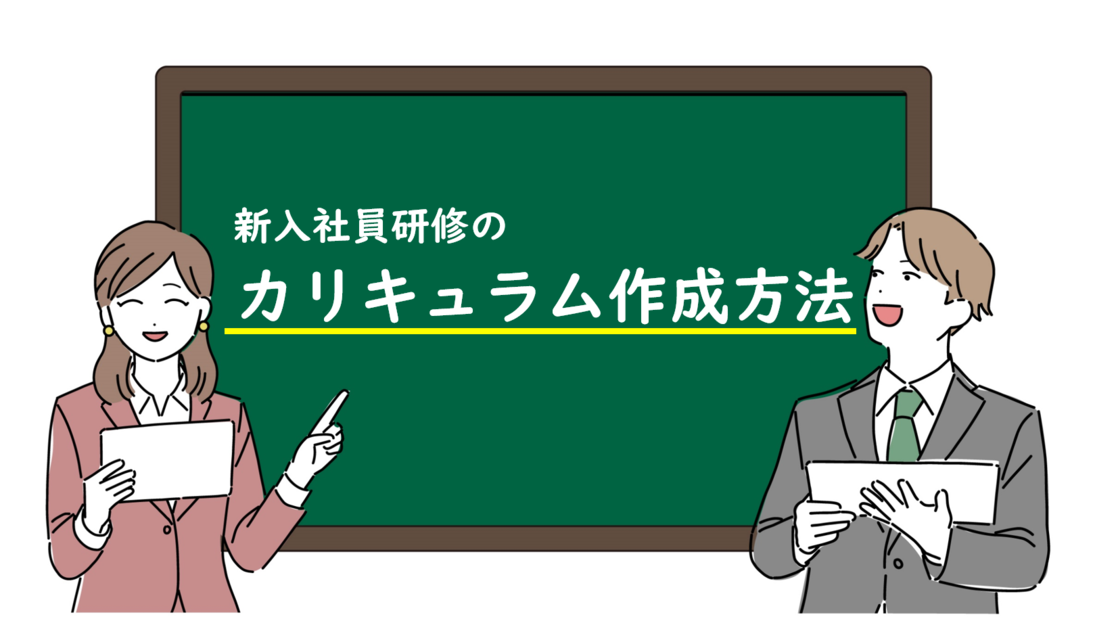
アフターコロナになり、新入社員に求められる研修は大きく変化しました。もちろん、業種や職種によっては今までの研修もニーズはあります。しかし、オンライン化に伴いITスキルや対人スキルなどが今まで以上に重視されているようです。カリキュラム作成では、次の6つのポイントに沿って作成してみましょう。
(1)新入社員の基礎力把握
時代の移り変わりとともに、学生の持つスキルにも違いがあります。最近の学生は、PCを触ったことがなく、スマホで完結する人も多いです。業種・職種によって求められているスキルに違いはありますが、人によって持っているスキルは違うため、事前に把握しておく必要があります。
(2)現場からのフィードバック
今までは、経済産業省が掲げる3つの能力(前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力)に分類される12の能力要素[2]のようなスキルが求められてきました。しかしパンデミックによる不測の事態に側面し、現場ごとに新たな課題が出てきたのではないでしょうか。
業種や職種によりますが、今後は社会人としての基礎力だけではなく、ITリテラシーやLGBTQ+など、現場からのフィードバックを元にした研修を導入する必要があります。
(3)目標設定
新入社員の基礎力や現場の求めるスキルを把握したことで、いよいよ目標設定ができます。カリキュラ作成において、目標設定を先に掲げる手法は多いです。しかし、この手法では研修と現場との間に差が生じてしまうでしょう。現場にとっては二度手間に、新入社員にとっては不安や戸惑いに繋がってしまいます。細かい目標設定は、研修内容の構築の際に行いましょう。大枠となる「新入社員にどのようなスキルを学んでほしいのか」を押さえて目標を立てていきます。
(4)研修内容の洗い出し
新入社員にどのような研修を行うか。現場からのフィードバックや新入社員のスキルを加味した上で、箇条書きしていきます。期間のことは考えず、何が必要か・どんな人材になってほしいか、企業ごとの考えを踏まえ、思いつく限りの案を出してみましょう。研修内容の箇条書きによって、書き出した内容をグルーピングし、どのような研修を行うか案をまとめます。
(5)研修期間の算出
研修内容が決まったら、時間を算出します。企業によっては、目安となる研修期間が設けられていますので、枠組みに沿う研修内容を足し引き、または掛け合わせや割愛していきます。
(6)研修内容の構築
研修の流れが決まったら、当日の運営をシミュレーションします。実際の運営ではイレギュラーが発生することを念頭に入れて取り組む必要があるため、時間や研修内容に余裕を持たせておくとよいでしょう。
■新入社員研修に取り入れられるカリキュラム手法
研修内容が決まったら、どのような教え方が適しているか考えていきます。教え方には、次の表に挙げた7つの手法があります。それぞれの特徴を押さえ、研修内容に適しているか確認しましょう。
| 手法名 | 概要 |
|---|---|
| OJT | OJTとは「On the Job Training」の略で、実際の現場で働きながら能力を上げていく手法。 |
| OFF-JT | OFF-JTは「Off the Job Training」の略で、実際に勤務する現場とは違う場所でおこなう手法。 |
| ロールプレイング(ロールプレイ、ロープレ) | 参加者それぞれが役割に分かれて演じることで、現場で起こるシチュエーションを疑似体験する手法。 |
| グループワーク | グループで話し合い、課題を解決していく手法。 |
| ケーススタディ | 現場で実際に発生した事例をもとに、適切な対応の仕方や解決方法を学ぶ手法。 |
| レクリエーション | 簡単なゲームや課題を通して学ぶ手法 |
| メンター制度 | 所属部署以外の先輩社員が新入社員をサポートする手法 |
■新入社員研修の用途に合わせた会場選びは大切

研修内容によっては、オンラインで完結するものもあれば、実際に対面の場を設けた方がよいものもあります。対面の場では、三密回避が必須と言えるでしょう。
エッサム神田ホール2号館には、天井の高さ3.6mの開放的な会議室がございます。今後も求められる三密対策のレイアウトによって、ソーシャルディスタンスを確保しつつ、新入社員研修を実施可能です。詳しくはレイアウト一例をご覧ください。
エッサム神田ホールでは、研修会場のご予約を1年前から仮予約の受付をしております。毎年4月はご利用が集中しますので、お早目にお問い合わせください。
その他にもエッサム神田ホールならではのサービスとして、オンラインとオフラインの研修を同時開催できる「ハイブリッド型セミナー」をご用意しております。ハイブリッドセミナーの詳しいご紹介は、「ウィズコロナ・アフターコロナ時代の新たなセミナー形式とは?」をぜひご一読ください。
参照元:
[1]^HR総研:人材育成「新入社員研修」に関するアンケート調査 結果報告(2020年)https://hr-souken.jp/research/2550/
[2]^経済産業省, 社会人基礎力https://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/index.html
2022年03月31日の記事を再編集しました。
