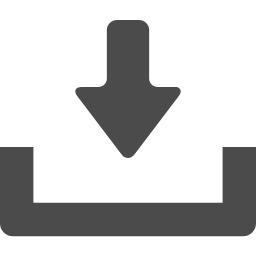- 東京都内の貸会議室 エッサム神田ホール
- コラム記事一覧
- 会議の司会進行を任されたら司会者が心得ておくべき14のこと
会議の司会進行を任されたら司会者が心得ておくべき14のこと
2022年 12月 28日

みなさんは会議の主催者として司会を行うケースがどのくらいあるでしょうか?
週に何度も司会をする人もいれば、年に1度程度しか司会者を務める機会のない人もいると思います。司会をあまりしたことがない人にとって、司会をするのはすごく気が重いですよね。司会が上手にできる人を見ると、つい「あいつは司会の才能があるんだろうなあ」と思ってしまいがちです。
ですがそんなことはありません。司会心得のポイントさえ押さえれば、意外と簡単にできてしまうんですよ。
では司会者として会議を上手に進められる人は、一体、どのような心得を持っているのでしょうか。
今回は会議を主催し、自らが司会者となる場合に心得ておきたい14個のポイントを紹介します。
1:会議までに進行表を作成・配布しておく

まず、"どのような会議進行にする予定なのか"一覧表を作成します。
一般的には「アジェンダ」と言われるものです。
内容としては、
- 日時
- 場所
- 参加者名
- 会議の議題と目的
- 議案内容にかける時間と具体的な時刻
が、A4サイズ相当の分量で盛り込まれていることが理想です。
進行表は参加者に会議の意味を理解してもらい、スムーズな会議進行を実現させることに意味があります。そのため、長々とした進行表では参加者が事前に目を通すことが億劫になってしまい、進行表を作成する意味がなくなってしまうでしょう。
また、作成した進行表は可能な限り、会議前日の午前中までに配布を完了するようにします。
配布をするタイミングが早いと、作成した進行表がどこかに紛れ込んでしまい目を通してもらえない危険性があります。また、配布が会議直前すぎてしまうと参加者が進行表に目を通す時間がなくなり、進行表を作成した意味が薄れてしまいますので、注意が必要です。
2:議事録係を頼んでおく
効率よく会議を進行するためには、司会者は司会進行に専念するべきです。よく司会者が自ら議事録をとるケースを見かけますが、議事をとるたびに進行が妨げられてしまうため、それだと時間が間延びしてしまうことも。もし重要な内容が抜け落ちた議事録が出来てしまったら、内容の再確認が必要になるなど、非効率です。
会議を開催するときには必ず議事録係を決めておきましょう。また議事録を作成する人は誰でも良い訳ではなく、同じ部署のメンバーが望ましいです。可能であれば会議の議題に関して、基本的な内容をある程度把握している人が適任です。
他の部署でかつ異なる分野の人が議事録を作成しようとすると、用語の意味や議事の内容が理解できず、発言者の内容を聞き逃す可能性が高くなります。完成した議事録の内容がイマイチで、会議後に発言者に再確認する手間が発生する可能性もあります。
3:会議の議題と目的は5W2Hでまとめる
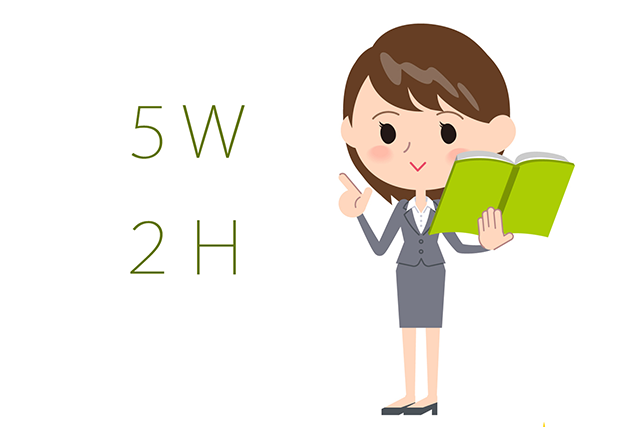
すべての参加者が、事前に会議の議題と目的を理解していれば、不要な議論を防げます。そのためには会議の議題と目的が明らかになっている必要があります。
その時にぜひ使って欲しいフレームワークが「5W2H」です。
「5W2H」とは
- When:いつ
- Where:どこで
- Who:誰が
- What:何を
- Why:なぜ
- How:どのように
- How much:いくらで
です。
今回は上手く会議を進めるための事前準備に「5W2H」というフレームワークを使ってみましたが、「5W2H」は他のシーンでも使えます。例えば、営業やマーケティングなどの分野において何か企画立案をする時です。「5W2H」のフレームワークを当てはめることで、検討する対象が抜けていないかチェックがしやすくなります。
4:会議当日の司会進行を把握しておく
会議によっては、司会とファシリテーター、それぞれを用意して会議に臨みますが、場合によっては兼任する人も。
会議をアジェンダに沿って行えれば、大きなトラブルは起こりにくいですが、必ずしも上手く行くとは限りません。事前に会議の大まかな流れを把握しておくことで、脱線した際の軌道修正や意見が出ないときの沈黙を打破できる声掛けの準備ができます。
司会とファシリテーターがそれぞれいる場合は、互いに連携を取れるよう事前に打ち合わせをしておきましょう。
会議進行に今すぐ使える便利なフレーズとコツを知りたい人はこちら
>>デキる会議のファシリテーターが使っているアジェンダと便利なフレーズ9選
5:参加者がどのような発言をしそうか事前想定する
会議を開催することが決まった時点で、参加者も自ずと決まるものです。
参加者によっては会議の議題に対して文句を言いそうな人もいれば、文句は言わないまでも多面的かつロジカルに質問を投げかけてくる面倒な人もいるでしょう。
会議が始まる前までに、誰がどのような発言をしそうか事前にシミュレーションし、回答例をいくつか作っておきましょう。
そうすることで、文句を言うような参加者や面倒な質問を投げかけてくる参加者に対しても、会議途中でしどろもどろすることなく、理路整然と納得感の高い回答が可能となります。
6:議事進行が崩れた場合の対策を立てておく
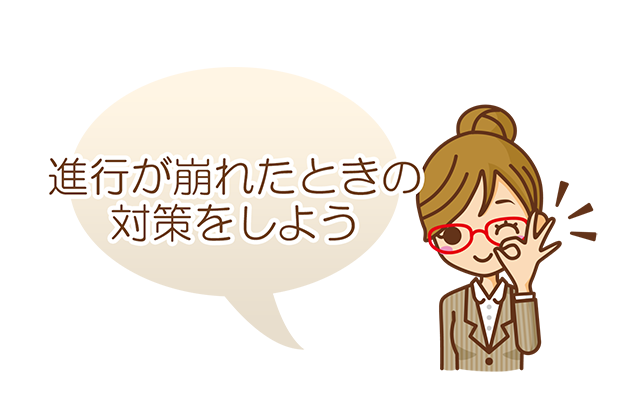
会議内容が白熱すればするほど、予定していた時間配分通りの議事進行が難しくなり、会議内容が雑になってしまう可能性があります。そうならないためにも、会議前に議事進行が崩れた場合のシミュレーションや対策を立てることが重要です。
対策の立てる際のポイントは2つあります。
1つは先にも述べた通り、「参加者がどのような発言をしそうか事前想定すること」です。予想外の議事進行はある程度、防げるでしょう。
もう1つは時間配分通りの議事進行が難しくなった場合、次回以降に議論を持ち越しても良い議題を想定しておくことです。そうすることで、結論が出ずに会議が終わるという最悪のケースは避けられます。
7:会議の冒頭に「ゴール」を明示する
会議の前に参加者に対して進行表を配布していたとしても、会議冒頭で必ず、会議で議論したい内容と目的を明示しましょう。それに加えて、「今回の会議のゴールは○○を決めること」「今回の会議では○○の結論を出すことがゴール」というように、参加者に対して宣言するように心がけます。
そうすることで、参加者の頭の中に改めて「ゴール」が見えます。
すると、参加者全員が、そのゴールに向けて自然と建設的な議論を進められるようになるのです。また、仮に参加者の誰かが会議の進行を乱したとしても、他の参加者が上手くフォローをしてくれることもあります。
8:会議は時間厳守を心掛ける

会議を始める際に参加者の集合が遅く、毎回定刻より開始時間が10分遅れることはありませんか?
また、いつも定刻の時間で終われずに10分・20分の延長が発生してしまうことは?
会議の参加者たちは基本的に意思決定ができる人やその分野の説明ができる人を中心に構成されます。つまり、忙しい人ばかりだと言っていいでしょう。
そんな忙しい人たちの間で「あいつが司会をする会議はいつも10分遅れで始まるから、ゆっくり行けば大丈夫」「あいつが司会をすると会議がいつも定刻で終わらないから参加したくない」といったネガティブな噂が社内に出回ってしまうかも...。
会議は事前の連絡と準備をしっかり行って、時間厳守で進行しましょう。
9:本題前にアイスブレイクを設けると有効
会議の本題に入る前は、参加者をリラックスさせて、コミュニケーションがとりやすい環境を準備しましょう。特に他部署の人や取引先などの外部の人が出席する場合は、コミュニケーションがとりづらい雰囲気を極力取り払う必要があり、そんなときにアイスブレイクは効果的です。
具体的なものをいくつか紹介します。
初対面の参加者であれば、自己紹介トークをして初対面という認識を取り払う方法があります。簡単なゲームをとりいれたり、会議内容とは違った話題を用いて雑談をしたりするだけでも良いでしょう。
会議時間が限られている場合は簡単な体操をとりいれたり、飴やお菓子を配ったりする程度の行為でも、アイスブレイクとしての効果が期待できます。
アイスブレイクについてはこちらの記事も参考にしてください。
>>定番から変わり種まで、会議の緊張を一気にほぐすアイスブレイク集
10:司会は身振り・手振りを大きく、熱意をもって!

いくらしっかり会議に向けた事前準備をしたとしても、司会者が「やらされている感」満載で議事進行をしたら、どうでしょうか?参加者のモチベーションは上がらず、会議の雰囲気はだらけたものとなってしまいます。
司会者が情熱をもって議事進行をすると、表情だけではなく身振り手振り・声の張りなどから参加者に熱意が伝わりやすいです。すると議事進行に多少の落ち度があったとしても、司会者の情熱が参加者を引っ張り、議題の目的を達成できます。
自らが会議の主催となって司会者を務める時には、「会議を成功させたい」という情熱を上手く活用して下さい。
11:一つひとつ議題を消化、終わったものと未解決のものを明確に
終わった議題は進行表に線を引くなどして、一つひとつ消していきましょう。議題の進行を把握することは最も重要です。進行を目に見える形にすることによって、だらだらと会議が蛇行することを防ぐ効果があります。
また終わっていない議題を明確にしておき、次回へ持ち越すべき議題か、進行順序を変えて後に回すべきかをハッキリさせておくと、より効率よく議題を進行できるでしょう。
議題が途中で変更になったり、新たな議題が発生したりする場合もあります。議事録担当者が記録に残すだけでなく、参加者がメモ書きを残しやすいような進行表にレイアウトを工夫しておくと、会議の進捗具合を全体で共有しやすくなります。
12:発言していない人からも意見を引き出す
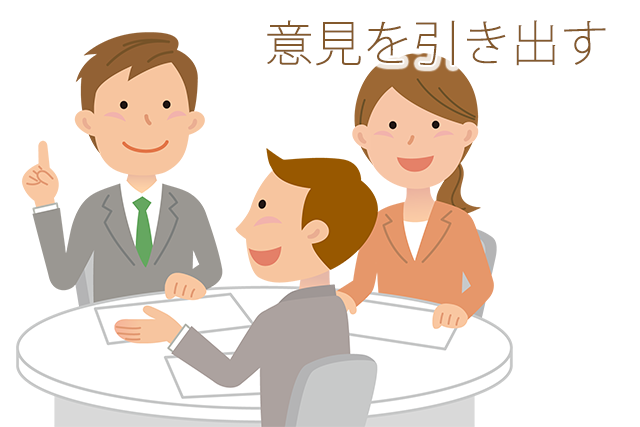
会議は参加者全員が参加しないと意味がありませんので、発言していない人からも発言してもらえるように進行することが大切です。特に部下の参加率が多い会議では、上司や先輩社員に遠慮しがちな雰囲気になります。
できるだけ、歳の近い部下に「○○さんはどうですか?」などと話を振って、「この意見はどう思いますか?」などと、発言につながる誘導をすると良いでしょう。
また上司の意見にみんなが賛成して、他に意見が挙がらないという状況も起こりがちです。無礼講とまでは言わずとも、極力自由な意見が出るようにして、意見が偏らないような配慮も大切です。
可能な限り、参加者全員が発言できるような雰囲気をつくりましょう。
13:最後に決定事項を読み上げる

その日の会議で何が決まったのかをまとめておき、会議の最後に読み上げることで参加者に確認をとります。これを怠ってしまうと会議に費やした時間が無駄になってしまいます。
時間の制約が厳しい中では最後の決定事項が十分に確認できないまま終了するケースが多いようです。次の会議のときに「この議題、前回話さなかったっけ?」という事態の原因にも繋がりますので、その会議での決定事項は明確にしておき、議事録にも確実に残すようにしましょう。
14:議事録を24時間以内に共有する
議事録係と連携し、出来るだけ早く作成することが重要です。完成した議事録は少なくとも司会者が内容を確認するようにしてください。その他にも、会議に参加した数名に、配布前の事前チェックをしてもらいましょう。誤字脱字や内容の不備・食い違いがあると、読みにくいばかりか、参加者が誤った認識を持ってしまう可能性もあります。
また極力24時間以内に参加者へ共有することを心がけてください。時間をおいてから作成しようとすると、会議で取ったメモから思い出せる内容がどんどん減ってしまいます。
議事録作成後の共有方法を、事前に参加者へ確認しておくことも重要です。メールでの送付なのか、クラウド環境にアップロードするのかなど、参加者に合った配信方法まで詰めておくことで、会議の内容をスムーズに共有できます。
議事録の作成についての大事なポイントは、こちらの記事も参考にしてみてください。
>>上司を唸らせる議事録を作ろう!会議中と会議後のマル秘テクニック!
まとめ

以上14個が、自らが会議を主催し司会者となる場合に心得ておきたいことです。心得の多くが会議を始める前の準備に集約されていたことに気付かされます。何事も準備をすることは大切なことなのです。
ちなみに、みなさんは1時間の会議を開催することに関してどのくらいのコストが掛っているかご存知ですか?「社内の会議室を使っているし社内の備品を使っているのにコスト?」と思う人がいるかもしれませんね。
実は、会議にかかるコストの多くは人件費です。例えば、年収500万円(時給にすると3000円相当)の人が10人集まって1回1時間の会議を開催すると、人件費だけで3万円もかかっているのです。
上手な会議進行はコストを掛けた甲斐のある有益な時間へと繋がります。そして、情熱ある司会進行は参加者のモチベーションを上げ、より良い結果を導けます。
「あの人が司会をする会議は出席して気持ちがいい」と言われるような会議進行になるよう、これらの心得を実践していきたいものですね。
もしも会議を貸し会議室で行うことが決まったら、当日の司会進行をスムーズにするためにも事前に会議室のアクセスや広さ、備品を確認しておくのがオススメですよ。エッサム神田ホールへの行き方はこちらからご確認ください。
2016年09月08日の記事を再編集しました。